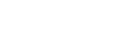建物とその周辺における健全な水環境の形成に関する考え方

1.安全の確保と健康の維持
建物とその周辺で使用される水は安全であること。建物内に居住する人のみならず、建物とその周辺各部に被害をもたらすことがないものとする。人が健康であるためには衛生性の確保が必要であり、良好な水質が維持されなければならない。また、文化的に居住するための水量の確保も必要である。これらのために、建物内に存在する水は汚染されることのないように計画し、適切に管理する必要がある。さらに、存在する水が時間とともに水質劣化する環境にある場合は、良好な水質を維持するための対策が必要である。
<安全な水の供給>
飲用に供される水を建物内で劣化させることなく、法律で定められている場合はそこで規定されている水質基準にしたがって水を扱う装置を計画する。同様に給水装置が設置された後は基準を維持するように良好に管理する。また、飲用以外に使われる水で人が接触する可能性のある場合は、飲用水に準じる水質で計画し、維持・管理する。さらに、建物及び敷地内の水景用に貯留されている水は、汚染されることなく良好な水質を維持する。
水を扱う装置や環境が、安全に運用できるように配慮する。
<害を出さない装置の構築>
人に対して健康被害をもたらすことがなく、漏水などにより物的被害を起こさず、使用時の騒音振動などにより居住者に不快感を与えないように水を扱う装置を計画・維持する。また、使用後の水は、人に害をもたらす物質が含まれている場合があり、人に触れることがないように速やかに排出する。
さらに、排水再利用に当たっては再生水の水質保全とともに、処理後に出てくる汚泥が人や建物の構成部分に害を及ぼさないように計画運転する。
<緊急時の水の確保>
災害などの緊急時に必要な水を、水質・水量を考慮して提供できるようにする。避難拠点などの重要な建物では、必要十分な水質と水量が確保できる装置を備え、災害時に破壊されないよう堅牢にする。また、水を扱う空間の安全性や快適性の確保に配慮する。
<空気環境に関わる水の配慮>
湿度の調整等で、水の飛沫や拡散などの有効活用を図る。また、空気環境に害を出さないよう配慮する。
2.自然との共生
水道は、主に遠くの水源から供給されている。また、過剰な地下水の汲み上げや湧水活用などは、地下の水環境に悪影響を与える。さらに、多量の雨が河川や下水道へ排出されることにより、内水氾濫等の問題を引き起こしている。雨などの近くで得られる水を活用し、近くで大地・空に戻すことが健全な水環境の基本である。
一極集中形のシステムにとらわれず、水や緑、光、空気などの環境要素を活用することを考慮する。
<地域における水資源の利活用>
散水や魚の飼育など、人が飲用したり、触れることがない用途の水は、敷地及び建物に降る雨などの近くで得られる水を、その用途に適する水質を考慮しながら利活用する。
<雨水排水における配慮>
地域・土地の特性をとらえて、敷地内に緑地を増やし、降水を敷地で浸透させたり、一旦貯める等の工夫により流出を抑制する。
<排水の水質に対する配慮>
環境に負荷をかける水質がある一方、養分を供給する水質もある。それぞれについて検討し、有効活用を図る。
<水の熱的資源性の活用>
水は、温まりにくく冷めにくい蓄熱性を持ち、蒸発により周囲の熱を奪う。そのような水の持つ熱的資源性を活用し、自然の資源とエネルギーを活用しながら熱を蓄え、微気象の改善を図る。
<自然生態系への配慮>
土地の開発においては、生態系を構成する動植物などの生物的要素と水・空気・土・光などの非生物的要素の保全に配慮する。また、造成した土地における生態系の創出に努める。
3.省資源と省エネルギー
水を扱う装置は、人間の生活と直接関わる接点に位置し、環境への影響は多大である。また、その設備を計画・設置・運用するにあたっては、外部環境に及ぼす負荷を極力減らし、そこで消費される資源・エネルギーを少なくしなければならない。そのためには、計画・設計・施工・運用・改修・廃棄の各段階で、いかに資源・エネルギー消費量を削減でき、かつ環境負荷の低減が可能であるかを検討することが重要である。さらに、計画から廃棄までを通したライフサイクルの中で、エコバランスや廃棄物削減を考慮することも必要である。
<節水の推進>
節水は、使用水量の節約はもとより、下水量を減らし、上水・下水配管への負荷低減につながる。また、関連する装置の機器容量・使用材料を減らすとともに、維持管理に伴うコスト・エネルギーを削減する。さらに、地球環境負荷を低減する効果がある。
節水の第一歩は、使用者の節水意識と生活スタイルであり、節水意識は、日常の節水行為はもとより、節水型機器を選択する動機にも反映する。使用者に節水意識を普及させるとともに、安全かつ衛生的で、合理的な水使用が確保されるよう、計画、設計における配慮と、節水機器・システムの定着を図る。
<水の有効利用の推進>
雨水及び再生水は、トイレ洗浄水・散水・洗車用水・水景用水などへ活用を図る。また、都市の排水負荷低減・非常時の緊急用水・洪水時の治水対策など社会的な貢献もしているため、水需給の増大・ひっ迫している地域を中心に導入を進めていく。
<装置における省エネルギーへの配慮>
水を扱う装置における水の搬送は、ポンプの効率を向上させるとともに、配管長の短縮などによって、圧力損失の低減を図る。また、給湯熱源機器の省エネルギーは、機器自体の効率に依存する部分が多いため、使用実態を把握して、省エネルギー性を向上させる。さらに、熱源に自然エネルギー・未利用エネルギーを活用する機器・システムの開発を進める。
<環境への負荷が少ない最適な方式の導入>
水を扱う装置の計画にあたり、敷地周辺の自然条件及び都市基盤施設である上水・下水・ガス・電気・通信などに関する情報を収集・分析したうえで、集中することのみにとらわれず分散を図るなど、周辺環境に対して負荷の少ない調和のとれた最適な方式を導入する。
<機材の再使用・リサイクルの推進>
水を扱う装置は、性能・品質の確保、生産性の向上などに加えて、環境への配慮が求められている。そのため、資機材はエコマテリアルの採用を考慮するとともに、リユース・リサイクルにより、廃棄物の発生が抑制され、省資源化が図れることから、経年による劣化を考慮し、安全性・衛生性が確保されていることを条件に、これらの利用拡大を図る。
4.社会資産の形成
健全な水循環の形成には、水を扱う装置や水景が世代を超えた社会資産となるように長期間維持することが重要である。水を扱う装置は、耐久性のみならず、社会的な要因による要求性能の変化により、長期間性能が維持できないものもあるが、建物の長寿命化に伴い、高い性能を長期間維持できるようにするとともに、補修・改修に継続的に対応する必要がある。また、水景は、建物の内外において重要な景観を形成するために整備されているが、適切な維持管理がなされないために、長期間にわたって良好な景観を維持できていないものが多く見られる。自然との共生を図りながら周辺環境になじむ水景を創出する必要がある。
<装置の長寿命化>
水を扱う装置は、高い耐久性と社会的な要求性能を持たせることで、長期間にわたって使用できるようにするとともに、補修や交換を容易にすることで、長期的な維持管理を可能にする。
<計画的な維持管理>
水を扱う装置は、使用中に所定の機能を保持し、常に安全かつ快適な環境が確保できるように機器の使用目的・構造・材質の違いを考慮した維持管理基準を定め、計画的な日常管理・定期点検及び保全整備を行う。また、維持管理の情報を提供し、建築設備の価値が高く評価されるような社会環境の形成を図る。
<景観の保全と創造>
水景の創出においては、地域の良好な景観を形成するよう、周辺環境との調和を図るとともに、生物の生息場所の確保に努める。そのために、空間配置や使用する素材に留意するとともに、湧水などの天然資源を活用することで、持続可能な空間を維持する。
5.将来世代への継承
私たち人間は、水循環の一通過点として、生命を育むため、また生活を営むために取水と排水を繰り返している。しかし、これらの活動を通じてなんらかの水質汚濁が生じる。私たちの生活や社会の土台となる建築生産も例外ではない。安全で安心して暮らすための健全な水環境を形成するには、建築生産における取り組みが不可欠である。そのためには、生活空間の中に水の大切さや重要性を感じることができるような建築的な配慮や、建築生産によって水環境に与える悪影響を極力抑えることが必要である。日本の給排水衛生設備技術は世界の最高水準にあり、先進的な技術開発と建築生産を通じて、新たなライフスタイルを先導的に提案していくことが必要である。これらの活動は、分野を超えて専門家が協力し、地域と連携して取り組むことが求められる。
<水の大切さを認識させるまちづくりや教育の推進>
都市や生活空間における様々な姿の水資源としての活用・水循環を可視化し、私たちの生活と水環境が密接に関係していることを認識できるようなまちづくりを進める。また、子どもを中心に健全な水環境の大切さを伝えていくために、目に見える方法での教育や建築生産を推進する。
<技術及び文化を継承するための情報の整備>
健全な水環境の形成に使われた知識・技術・資機材・活動及び完成した建築と都市の環境に関するすべての情報を蓄積・共有し、次世代に正確に伝達できるような情報基盤を整備する。また、多くの分野が連携して情報を有効活用し、継続して情報基盤を運用していくための社会システムを構築する。
<水の確保と衛生の改善に関する支援及び協力>
健全な水環境を形成することは、地球レベルでの重要な課題である。発展途上国での安全な飲料水と地域に適した衛生設備の整備を推進するため、人材育成と技術支援を積極的に行い、地球規模での水環境の改善と安定的な発展を図る。
前文
水は、地球上の限りある資源であり、すべての生命に欠かせないものです。人は水を治め・利用し、さらに水まわりの空間や装置を創りだすことで、健康・安全で快適な生活を実現してきました。
その一方で、安全や健康に関する新たな課題が発生しています。また、開発に伴う害の発生や自然生態系の縮小が進み、さらに、資源やエネルギー消費の増大による廃棄物の増加や地球温暖化、都市におけるヒートアイランド現象が顕在化しています。
今、人間の健康と安全を図りながら、持続可能な社会を実現していくことが大きな課題です。
建物とその周辺における水環境は、それ自体完結したものとしてではなく、地域の水循環と社会基盤との関係においてとらえなければなりません。
開発者、設計者・施工者・管理者、居住者など建築に関わるすべての人々とともに、建物とその周辺における健全な水環境の形成に努めたいと考えます。
2008年12月
1.安全の確保と健康の維持
-
•安全な水の供給
-
•害を出さない装置の構築
-
•緊急時の水の確保
2.自然との共生
-
•地域における水資源の利活用
-
•雨水排水における配慮
-
•排水の水質に対する配慮
-
•水の熱的資源性の活用
-
•自然生態系への配慮
3.省資源と省エネルギー
-
•安全な水の供給
-
•害を出さない装置の構築
-
•緊急時の水の確保
4.社会資産の形成
-
•装置の長寿命化
-
•計画的な維持管理
-
•景観の保全と創造
5.将来世代への継承
-
•水の大切さを認識させるまちづくりや教育の推進
-
•技術及び文化を継承するための情報の整備
-
•水の確保と衛生の改善に関する支援及び協力
社団法人 日本建築学会
環境工学委員会 水環境運営委員会
〒108-8414 東京都港区芝5-26-20 Tel. 03-3456-2051
日本建築学会ホームページ
http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm
水環境運営委員会ホームページ
http://news-sv.aij.or.jp/kankyo/s21/
この考え方は、環境工学本委員会の承認を得て水環境運営委員会の責任において表明するものです。
起草
水環境憲章小委員会(2005年4月〜2008年3月)
健全な水環境の形成検討小委員会(2008年4月〜)
主査:長尾良久(TOTO)
幹事:小瀬博之(東洋大学)
委員:
浅野良晴(信州大学)
大塚雅之(関東学院大学)
加藤 篤(日本トイレ研究所)
黒岩哲彦(アルキテクタ)
高地 進(ピーエーシー環境モード)
中久喜康秀(竹中工務店)
元委員:川人尚美(竹中工務店)
運用
水環境運営委員会
2009-2010年度委員
主査:
小瀬博之(東洋大学)
幹事:
大塚雅之(関東学院大学)
坪井塑太郎(産業環境管理協会)
委員:
浅野良晴(信州大学)
王 祥武(須賀工業)
屋井裕幸(雨水貯留浸透技術協会)
神谷 博(設計計画水系デザイン研究室)
倉田丈司(INAX)
畔柳昭雄(日本大学)
関 五郎(日建設計)
高地 進(ピーエーシー環境モード)
高橋紀行(竹中工務店)
長尾良久(TOTO)
野崎利樹(都市再生機構)
野知啓子(関東学院大学)
村川三郎(広島大学)
元委員:吉田良人(都市再生機構)
2008年度委員
主査:
小瀬博之(東洋大学)
幹事:
大塚雅之(関東学院大学)
王 祥武(須賀工業)
委員:
浅野良晴(信州大学)
井田光俊(オフィス I・D・A)
神谷 博(設計計画水系デザイン研究室)
倉田丈司(INAX)
黒岩哲彦(アルキテクタ)
関 五郎(日建設計)
高地 進(ピーエーシー環境モード)
高橋紀行(竹中工務店)
田澤龍三(清水建設)
長尾良久(TOTO)
野知啓子(関東学院大学)
村川三郎(広島大学名誉教授)
吉田良人(都市再生機構)
本文