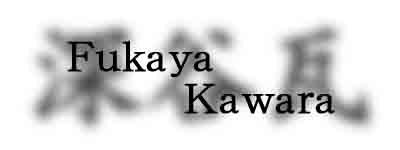
・深谷瓦の歴史 日本へ瓦が渡来してから1400年といわれている。 深谷では、奈良時代(国分寺が開かれたころ)の窯跡も出土していることと、 利根川が運んだ良質の粘土に恵まれていたことから、古くから瓦造りが行われて いたと思われる。 近世において深谷瓦の製造が盛んになったのは、江戸中期、徳川吉宗が町屋の 建築に瓦の使用を許可したころと思われる。 深谷瓦の最盛期は、太平洋戦争後東京大復興による瓦の需要爆発から昭和48年 の第一次オイルショックにいたるまでの約30年間であったといえる。 その後、まきや枝で焼くダルマ窯からLPGを使用したガス窯が普及するなどの 変化や需要減少による危機を乗り越えながら今日に至っている。 日本人が日本建築を愛する限りよい瓦への需要はなくならないという関係者の 信念と努力の甲斐もあって、ここ数年、需要が増加しているようである。 現在は、公共建物を中心とするRC建物への瓦使用の増大が大きな光明となって いるようである。よって、瓦業界の今後の課題は、高さの高い物件への安全な瓦 施工方法の確立といえる。 ・深谷瓦の特徴 ここの工場規模が小さいため、半手工的な生産方式をとっている。 コストは高いが、一枚の瓦が芸術品のように光り、大量生産の普及品と違って、 始めの光沢が良く、銀色のつやが長持ちするのが最大の長所である。 ・製造工程 ①原土処理―ロールクラッシャーによる粘土の中の小石の粉砕粒度調整 ②真空土練機―土中の空気を除去し密度を高め土を練る ③成型―金型によるプレス成型 ④仕上―バリをへらで削り形を整える ⑤乾燥―天日または窯の余熱による ⑥引き土―瓦の色艶や水はけを良くするため陶土を水にといたものを乾燥品に塗る ⑦窯詰め―窯は鉄板と断熱材でできた四角い箱になっている。瓦はコンテナと呼ば れる耐火煉瓦の棚に一枚ずつつめられる。 ⑧焼成―最高焼成温度950〜960度、約24時間で焼きあがる ⑨窯出 ⑩選別―選別は光沢、ねじれ、傷など目視検査で一級品、廃棄品に分ける ⑪変色防止剤塗布―変色防止のため、シリコンを瓦に塗布する。これは瓦の吸水を 少なくし、土中の鉄分の酸化成分が表面に浮いて瓦の色に悪影響を与えるのを防ぐ。 ⑫梱包 ⑬出荷 資料提供: 埼玉県瓦商工業協同組合連合会 深谷瓦商工業協同組合