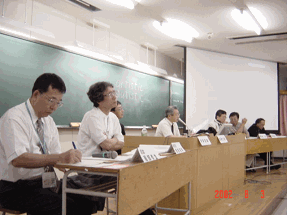2002年度日本建築学会大会研究協議会
これからの計画系教育はどうあるべきか
-計画系教育の変革のビジョン-
日時:2002年8月3日
司 会: 服部 岑生(千葉大学)
副司会: 岡崎 甚幸(京都大学)
記 録: 吉村 英祐(大阪大学)
| 主旨説明 |
岡崎 甚幸(京都大学) |
| 建築設計の現代状況と大学教育 |
服部 岑生(千葉大学) |
| 明確さと客観性に代わるもの |
伊東 豊雄(建築家) |
| 大学における建築計画教育の役割 |
柏原 士郎(大阪大学) |
| 都市計画教育の役割とビジョン |
北原 理雄(千葉大学) |
| 本当に生き生きとしたデザイン教育に向かって |
重村 力(神戸大学) |
| これからの計画系教育はどうあるべきか |
羽生 修二(東海大学) |
主題説明より
研究協議会では、計画系教育のビジョンを、計画系を構成する各分野のビジョンと分野相互間の討論により、主に以下の諸視点から明らかにする。 ①我国の計画系教育の特徴と反省、 ②21世紀社会の要求、 ③職能、 ④国際的技術者教育評価(JABEE)や建築家養成のための国際的教育評価(UIA)等の動向など。
我国の計画系教育の特徴は、計画系が構造や環境系と一体化し、計画系自体が多様な分野から構成され、多数の大学で教育が研究と共存し、創成型という新たな教育手法として他領域が注目する設計演習を併用するところにある。研究や設計演習の位置づけや多様な分野を統合する計画系全体のあるべき姿を探る。
計画系教育を取り巻く社会的環境は科学技術の進歩とともに変貌し、困難な課題(自然や歴史的景観の保存、情報革命、地球環境問題、都市と過疎等)が山積した。それが計画系の教育内容や価値基準を変えた。計画系教育はますますレオナルドのように知性と感あるいは理論と物の間の深淵を柔軟機敏に
飛び越える人材を養成する必要があるのか。さらに計画系卒業者が活躍する新たな分野を開拓するための教育ビジョンは、どのようなものか。
計画系の職能は医学や法学と同様、国民生活の基本的要求を満足する義務があり、そのために国家が認定する資格制度がある。しかし混乱する都市景観、荒廃した自然や歴史的景観は、この職能または職能教育や学会に対する警鐘ではないだろうか。法学等の専門大学院構想などを参考に計画系教育の職能面からの再考が必要であろう。
教育評価の国際化をめざし世界建築家連合UIAは、ユネスコとともに、「実務経験者中心の教授陣、5年以上の教育期間」等の諸条件のもとに建築家教育の国際的認定を構想している。もしUIAの条件を満足しなければ我国の学生や留学生は国際基準の教育認定を受けられない。技術系の国際的教育認定JABEEはすでに試行済みである。国際基準を満足する計画系の教育ビジョンは、どのようにあるべきか。
以上、計画系教育のビジョンは国民生活に不可欠であろう。
岡崎 甚幸(京都大学)
|