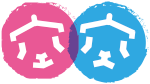 研究・好事例
研究・好事例
空き地 平時の都市計画につなげる空き地・空き家の編集
- 防災集団移転と移転元地
東日本大震災から10年以上が経過したとはいえ、この言葉をお聞きになったことのことのある方は多いと思います。もちろん実際にそれを経験された方もいらっしゃるでしょう。 震災復興においては、被災された方々がより安全な宅地に移転することを目的に、津波被害の危険性がある沿岸部に、災害危険区域を設定し、移転元の宅地を市町村が買取りました。
集団で移転することで、移転先でもコミュニティが再生することを期待した取り組みです。しかし、そこで問題になっているのが、移転の元地の将来像です。
いくつかの被災都市では、ある程度の規模の移転元地をそのまま大規模な公園にして、犠牲になられた方々を祈念する「場所」にしています。しかし、すべてそのような用途にすることは不可能です。災害危険区域への居住は原則的に禁止となるのが一般的です(自治体が条例を作って居住可能にしている地域もあります)。
住むことは出来なくても、そこで商売をしたり、様々な活動のための「場所」にしたいと思う人々は多いはずです。災害が起きた時の避難方法を真剣に検討した上で、そのような活用をしていくことが必要不可欠です。住宅を移転した場合には、その土地を自治体に買い取ってもらっていきますが、土地活用を考える方々は、そのまま土地を所有して、将来的にそれを活用することを希望していました。何しろその場所は震災が発生する以前は街の中心地だったケースが多かったのです。
そうすると、右の図を見てわかるように、すっかり土地所有者がいなくなった土地と、いずれ活用を考える所有者の土地とが、街の中に混在していくことになります。商業店舗を開発しようとする人、会社を再建する人、農地にしようと考えている人。土地が複雑に入り組んだ街区では、思い切った活用がなかなか難しいかも知れません。でも、持っているけれど活用の予定がない人がいるはずです。もしかしたら、土地を交換したり、場合によっては自治体がその土地を買い取って、多様な活用が可能となるある程度の規模を持つ敷地に編集することで、活用の道が拓けていって、新たな街の中心部がつくられることにつながるかもしれません。
図1 移転元地の編集(復興庁HP2)より)
そのような工夫をしないと、単に移転跡地になってしまいます。復興まちづくりの最前線で活躍されていた東松島市役所の小林典明氏3)は、「我々は跡地とは表現せずに、次の活用のための元地と呼ぶ」というお話をされていました。
空き地、そして空き家。かつてそこに存在していたはずの多様な物語。その再生を信じて復興まちづくりを進めてきた方々は、跡地として単なる「空間」を増やすのではなく、生きた「場所」として、そのための元地として活かしていきたいと考えています。
復興まちづくりの過程で出現していってしまう空き地を、将来のまちの姿に活かせるように考えている人々が東北の被災地にはいらっしゃいます。そしてそれは、復興現場だけではなく、私たちの平時の都市計画でも通用するヒントを示唆してくれています。 - 復興まちづくりから平時の都市計画へ
私たちの住む都市の中心市街地は、空洞化が進んでいます。空き地、空き家の問題は益々大きくなっています。復興のために自分たちが持っていた土地を自治体に売ったり、周辺の土地と交換して新しいまちづくりを目指す場面とは異なり、都市の中心部に存在する土地は、平時にはそう簡単に動くものではありません。まさに「不動産」なのです。しかも、地域には住んでいない土地所有者もかなり大きな割合で存在しています。そのような地域で、被災地の移転元地のように空き地を編集していく取り組みは、不可能なのでしょうか。
その意味から大きな可能性を感じる取り組みが、山形県鶴岡市で進められています。NPO法人つるおかランド・バンク(以下、ランド・バンク)の活動です。これまで中心的な役割を担ってきた前理事長の阿部俊夫さんがシンポジウム4)でお話しされた興味深い話をご紹介します。鶴岡市では中心市街地の「空間」の解消対策として、ランド・バンクが必要なノウハウを実践とともに蓄積してきています。普通、空き家バンク事業と言われる施策は、そのほとんどが空き家・空き地の情報を集めるデータベースで終わってしまうケースが多いようです。そこを鶴岡市では、宅地建物取引業協会、建設業協会、行政書士会、土地家屋調査士会、司法書士、建築士会、解体業といった専門家組織(士という名称が多く、さむらい集団と呼んでいました)と地元銀行、首都大学東京(現:東京都立大学)、地域のNPO、そして市役所が支援する形で活動を進めてきました。鶴岡のランド・バンク事業では、空き家の所有者と活用希望者のマッチングを行う空き家バンク事業とは違って、密集市街地の空き家・空き地を取得して、解体や整地、転売によって空き家と空き地、そして道幅の狭い道路を一体的に整備していきます。例えば、その道幅では新たに住宅を建築することが不可能な場所で、前に説明した被災地の移転元地の編集のように工夫をして、道路幅を6mに拡げて行きます(写真1)。
写真1 道を拡げて空き地を活用(鶴岡市)
このような空き地の編集作業は、復興という待ったなしの現場とは違い、まだその必要性を自分事として考えている人が少ないので、なかなか思うように進まないものです。その点、ランド・バンクでは上で説明した専門家集団が支援しています。復興の現場で進めている空き地編集の工夫は、平時の都市計画でも大変大きな効果をあげるはずです。
北原 啓司
参考文献
1)北原啓司:これまでの10年、これからの10年,造景2021,pp.154-161,2021年
2)被災市街地における土地活用の促進等に係るガイドブック低平地編(復興庁)
3)日本都市計画学会東北支部復興シンポジウム「防災集団移転の跡地利用はどう描か れるべきか」,仙台市,2013.7
4)「官民連携による空き家・空き地再生の可能性―鶴岡市を事例として―」,日本都市計画学会第39回都市計画セミナー,2016.1
