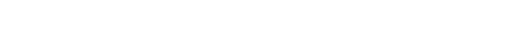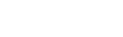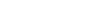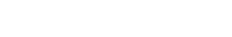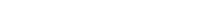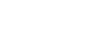(5)物質調達連鎖管理
これは、Supply Chain Management(SCM)と呼ばれるもので、環境に配慮した資材や部品を調達しているかどうかといった観点から環境に配慮しているか否かを検討するものであるが、建築物に関しては、この点を意識した取り組みは、一部のハウスメーカーにおいて見られるものの、広く行われている状況にはない。
(6)投資・金融市場における社会規範
工業製品にならって考えると、環境に配慮した建築物に対する投資や融資にインセンティブを与える取り組みがあるかどうか、環境配慮の建築物を建築する企業に格付けをする取り組みがあるかどうか、環境に配慮した建築物を購入することが推奨されている取り組みがあるかどうか、環境配慮の建築物を建築する企業に対する投資が社会的責任投資として認識されるかどうかといったことが問題となる。これらについては、わずかに住宅金融公庫が一定の基準等を定めて建築基準法の最低基準以上の水準へ誘導する施策(「長寿命」、「省エネ」、「バリアフリー」のうちの2項目クリアで基準金利を適用するなど)が論じられていた程度であり、その他少なくとも社会的に広く認知された取り組みは存在しない。
(7)建築物市場レベル対応
建築物が環境に配慮したものであることを対外的に端的に示す制度があるかどうかという点である。これについては、東京都が10,000?以上の述床面積をもつ大規模の分譲マンションについて、「建物の断熱性」、「設備の省エネ性」、「建物の長寿命化」、「みどり」という4つの環境性能を示すラベルの表示を販売広告に義務づけている。東京都のかかる取り組みは先駆的試みであるが、この種の取り組みが広がると、建築物購入者に一目で環境配慮建築物か否かが分かることになり、環境配慮の建物の建設を促進させることは疑いない。
しかしながら、建築物の景観配慮、さらには立地に適った空間の量の確保といった面では、現状では有効な対策は講じられているとはいえない。
(8)情報開示制度
建築物に関わる各種関係者が建築物についていかなる環境配慮を行っているかを情報開示するシステムが存在しているかどうかであるが、これについては、各企業が発行している環境報告書に記載することが考えられる。どのような評価基準で評価するかは確立しておらず、建築物についての環境配慮を開示している企業は先進的な取り組みを行っている若干の企業にとどまっている。ただ、今後、CASBEEの評価基準などが評価基準として確立されれば、建築物に関する情報開示も進むであろう。
一方、建築物の維持保全に関する情報については、開示はおろか、蓄積についても、明確な制度はまだ存在していない。建築物が数十年、あるいは百年を超えて使い続けられるような状況となった場合に、それが如何なる維持保全履歴を持つかについて、正確な情報を残すことは、長期的な利用を実現する上で必須の条件であると考えられる。例えば「建築物維持保全カルテ」と言った情報の伝達システムの整備が待たれよう。
(9)社会的責任の組織境界
会社の社会的責任をどの関連会社まで及ぼして考えるかという問題については、建築物を工業製品と異なって考えるべきものではない。但し、建築物が数十年、更には百年を超えて使い続けられるためには、建築の構成部位に応じて社会的責任の組織限界を設定する必要があるであろう。