住まいづくり支援建築会議
市民講座オープン=相談事例の失敗の予防と解決に有効な情報の講座を始めます。
設置の主旨
耐震強度偽装に関わる一連の不祥事は、建築の安全に対する国民の信頼を著しく毀損し、多くの国民に深刻な不安を与えることになった。日本建築学会は学術団体としての中立的かつ俯瞰的な立場から、不祥事の再発を防止出来る健全な設計・生産システムの構築を目指し、一般市民も含め産官学の関係者に向けて包括的対応策を示すとともに、その対策を実効あるものとするための活動を展開する。3月理事会に於いて、「健全な設計・生産システム構築のための提言の枠組」が承認され、日本建築学会として早急に取り組む課題を鮮明にしたところである。「提言の枠組」に示されるように、住宅・建築は国民にとっての生活基盤・社会基盤であり、地球環境の保全、文化の継承、安全安心の確保、少子高齢化への対応などの観点から、今後何世代にもわたって使うことの出来る持続可能なよりよき住宅・建築を、社会資産として次世代に残していかなければならない。住宅・建築の性能や構造安全性の水準を選ぶのは建築主および購入者であり、また住宅・建築は長期にわたって空間を占有し、環境および周辺住民に多大な影響を及ぼすとともに耐久財として流通していくことから、建築主・購入者は優良な住宅・建築を社会に存在させる責任を負っている。したがってよりよき社会資産の形成・継承という理念を実現するためには、建築主・購入者が住宅・建築に関してより正確な情報をもち自己の責任においてよりよい住宅・建築を創造していくことが必要である。
以上の基本認識の下に日本建築学会は、住まいづくりに関する社会状況を常時監視・評価し情報発信するとともに、社会課題について国民と社会が解決を要望する事項に迅速に対応する。具体的な活動事項として、建築主・購入者の住宅・建築への理解と認識向上に資するための基礎的知識を、ホームページや各種出版物の刊行、講演会・シンポジウム・見学会の開催等を通じて発信提供する。一方、これから住宅・建築を建築しあるいは購入しようとしている建築主・購入者が必要とする知識、あるいは建築後に直面している様々な問題等に関する情報を収集・分析し、関連分野の研究活動に反映させる。また、建築主・購入者からの直接的な相談事項について専門的知見を提供するなど、社会ニーズや社会とのチャンネル機能を重視した支援活動を展開する。さらに住まいづくりの関係団体と連携し、建築主・購入者の必要とする情報のネットワークを構築し、広く国民と社会の期待に応える。この活動を推進・実施する組織として、会長直属の会議体として「住まいづくり支援建築会議」を創設する。
活動計画
すでに建築主・購入者からの住まい相談関連事業は、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターをはじめとして、(社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会などの諸団体において先行的に実施されている。これら諸団体の活動に照らして、本会「住まいづくり支援建築会議」の支援活動は、住宅・建築に関わる各研究領域の調査研究の成果を発信すること、すなわち、建築主・購入者の建築への理解と認識向上のための情報普及事業を根幹とする。更に、情報普及活動を補完する活動として、調査研究と相談事項対応事業を実施する。第一段階として本部を中心に以下の三つの支援活動を行うこととして、支援建築会議の運営・管理を担当する運営委員会の傘下に、情報事業部会、調査研究部会、支援事業部会を設ける。本部に於ける支援活動が円滑に推進されるようになった段階から、各支部の協力を得て全国の活動へと展開する。
三つの支援活動と実施体制(図1〜図2)
第一に、建築主・購入者を対象とする住宅・建築に対する理解と認識向上のための情報普及活動である。住宅・建築の性能、安全安心問題、設計・生産の仕組み、建築関連法規、契約、専門用語、環境および都市問題、等々に関する基礎知識をホームページや出版物等の刊行を通じて提供する。また、講演会・シンポジウム・見学会などを開催する。この支援活動は情報事業部会が担当する。
第二に、本会をはじめ他の諸団体等に寄せられる建築主・購入者からの膨大な相談事項を収集整理し研究を要する課題について調査分析し、その成果を課題解決型の新たな研究課題として関係する調査研究委員会の調査研究活動に反映させる。また必要に応じて住宅・建築の維持改修、省エネなど要素技術の総合化、政策手段などについて自ら調査研究活動を行い、学術・技術の進歩発展に寄与するとともに政策提言として公開する。その成果は再び建築主・購入者に対する情報として還元される。この活動は調査研究部会が担当する。
第三に、関係団体に寄せられるなど想定される建築主・購入者からの相談事項を整理体系化して、求められる回答事例QAをホームページから検索出来る仕組みを構築し公開する。また、会議会員によるボランティア活動により、定期的な相談会を開催するなど優れた社会資産としての建築づくりを直接的に支援する。さらに高度な学術・技術的知見を要する相談事項については、文書などにより受け付け、調査研究委員会の協力を得て対応する。また相談会などの活動を行う関係団体とのネットワークづくりを行い、相談内容の精査・改善を行う。この活動は支援事業部会が担当する。
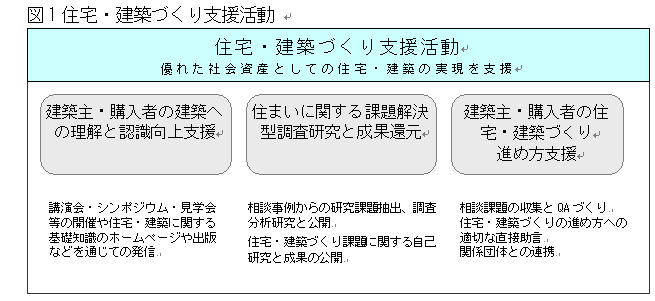
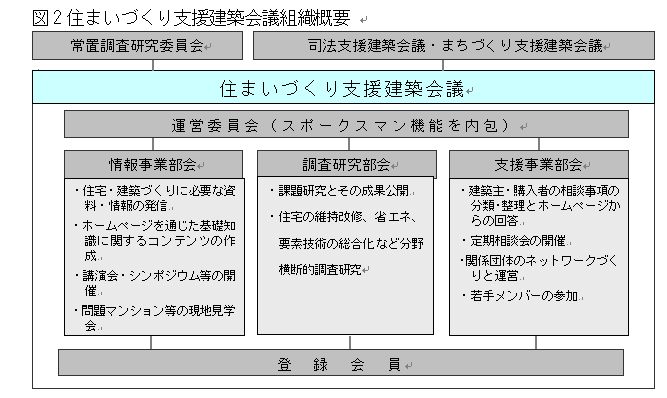
司法支援建築会議・まちづくり支援建築会議との連携協力
個としての住宅・建築の諸課題は、先行している司法支援建築会議との連携協力体制によって、また群としての住宅・建築の諸課題は、まちづくり支援建築会議の支援活動との連携協力体制を構築することで、総合的・俯瞰的に解決することが可能となり、より効果的な支援活動が期待される。
会議会員の登録(図3)
この支援活動は会員のボランティアとしての参加を前提として、支援業務に適切な学識・経験豊かな優れた人材を本会内の関係機関からの推薦を受けて、理事会の承認を得て支援会議会員として登録する。会議会員の人材データベースを構築し、講演会・シンポジウムの講師、出版物の執筆、相談業務等、適材にそれぞれ支援活動を担当頂く。データベースの構築と適材の配置などは運営委員会が担当する。
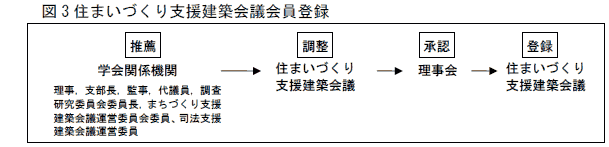
住まいづくり支援に関する住宅情報の関係(図4)
住まいづくり支援は、建築主・購入者が住まいづくりにおいて必要とする情報を合理的に提供し、その結果として建築主・購入者だけでなく、国民と社会が優良な住宅・建築のストックを獲得することを推進する。住まいづくりに関連して、建築主・購入者を取り巻き、公共団体、建築設計等の職能団体、建設業および情報産業が存在している。これらの関係団体は住まいづくり支援の意味の情報提供の機能を果たしている。この関係の中に、建築学会が入っていくことの意義、その中で合理的に住宅情報を提供することの目的は、学術団体として学術に基づく中立性�・客観性の立場からの情報発信である。その発信には、建築主・購入者の支援だけでなく、提言などの市民・社会への発信および政策提言などの行政への発信を含むものとする。
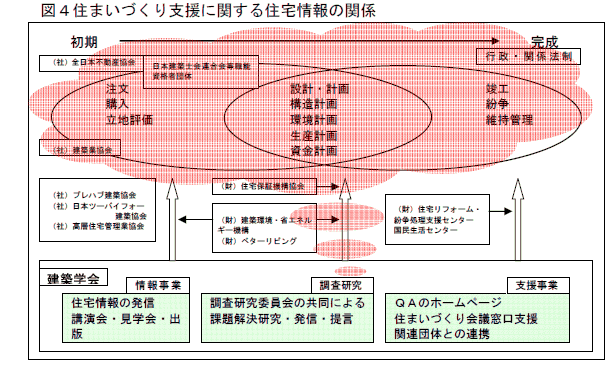
住まいづくり支援建築会議運営規程
2006年4月7日理事会決
第1章 総 則
第1条(名称)
この会は,国民がその生活基盤である住宅・建築をより良き社会資産の形成・継承という理念の下に実現することを支援するため、社団法人日本建築学会(以下学会とする)が会長直属の会議体として設置するもので,その名称は住まいづくり支援建築会議(以下会議とする)と称する。第2条(目的)
この会議は本会の学術団体としての中立公正の立場から、住宅・建築の安全や性能に関わる常置調査研究委員会、司法支援建築会議、まちづくり支援建築会議等との密接な連携の下に、蓄積される研究成果に基づき、国民の住宅・建築の購入や建築に際して必要な基礎知識、あるいは建築後に生じた様々な不具合の対処のために、講演会・シンポジウム・見学会等の開催、ホームページや解説書等の出版を通じた情報提供、相談会開催などの支援活動を通じて、優れた社会資産としての住宅・建築づくりを支援し,社会公共に寄与することを目的とする。第3条(事業)
会議は前条の目的を達成するために次の事業を行う。(1)住宅・建築の相談事項に関する調査研究
(2)住宅・建築の社会課題に対する意見表明
(3) 住宅・建築づくりの進め方や購入に際しての助言
(4)購入・建築後に生じた様々な不具合の対処への助言
(5)住宅・建築に関する講演会・シンポジウム・見学会等の開催
(6)住宅・建築に関するホームページや解説書の出版等を通じての情報提供
(7)関係諸団体との連携・情報交換
(8)その他前条の目的に沿った事業
第2章 会 員
第4条(会員)
会議の会員は、高い理想をもち中立公正の立場に立って、国民の優れた社会資産としての住宅・建築づくりを支援するものとし,豊かな学識経験を有する人格的に優れた者であって,原則として学会関係機関等※1ならびに第12条に規定する運営委員会から推薦された年齢50才以上70才未満の学会個人会員とする。【※1】理事,支部長,監事,代議員,調査研究委員会委員長,司法支援建築会議運営委員会委員、まちづくり支援建築会議運営委員会委員
第5条(登録)
会議の会員に推薦された者は別に定める登録申込書を提出し,運営委員会の議を経て学会理事会の承認を受けた後,会議会員の登録をする。第6条(退会)
会議の会員で退会しようとする者は,退会届を提出しなければならない。第7条(登録抹消)
会議の名誉を傷つけた,または会議の目的に反する行為のあった者は,運営委員会ならびに学会理事会の議を経て会員登録を抹消する。第3章 役 員
第8条(種類および定員)
会議に次の役員を置く。(1)会長 1名
(2)運営委員長 1名
(3)運営委員 15名以上20名以内
2.会長は学会会長が兼務する。
第9条(職務)
会長は,この会議を代表しその業務を総理する。2.運営委員長は会長を補佐し,会議全般の運営を司るとともに会長から委任された事項の会務を処理する。
3.運営委員は運営委員長を補佐し,この会議の業務を執行する。
第10条(任期)
会長の任期は学会会長の在任期間とする。2.会長を除く役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。(最長4年とする)
第11条(顧問)
会議に顧問若干名を置くことができる。第4章 会 議
第12条(種別)
会議は,全体会議及び運営委員会とする。第13条(構成)
全体会議は登録された個人会員をもって構成する。2.運営委員会は運営委員長ならびに運営委員をもって組織し、運営委員長は会長が指名し、運営委員は関係する常置調査研究委員会、司法支援建築会議、まちづくり支援建築会議から推薦された者、その他会長が理事ないし理事経験者から指名した者を学会理事会の承認を得て決める。
第14条(運営)
全体会議は必要に応じて会長が召集し,運営委員会は運営委員長が召集して開催する。2.全体会議は運営に関する重要事項を決定し,運営委員会は事業の計画と執行にあたる。
3.運営委員会には必要に応じて部会を設けることができる。
第15条(会議の存廃)
会議の存廃は,全体会議の議を経て学会理事会が決める。第16条(その他)
この規程に定めのない事項は,学会の一般規則を準用する。
![[住まいネット相談 ご案内]](sumai/images/button3_base.gif)
![[建築設計事務所実態調査報告]](sumai/images/button2_base.gif)
![[新築マンションを選ぶときには]](sumai/images/button1_base.gif)